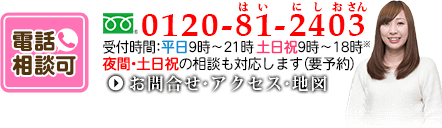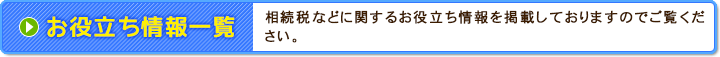相続税評価額の計算方法に関するQ&A
どのような財産が相続税評価の対象になりますか?
被相続人が持っていた現金や預貯金、自宅不動産など、民法上の相続財産に加え、相続税の計算においては生命保険金などのみなし相続財産も相続税評価の対象となります。
相続財産の評価額は、相続開始の日(被相続人がお亡くなりなられた日)を基準にして算定します。
また、相続税評価額の算定においては、財産の種類ごとに評価方法が異なります。
現金や預貯金はどのようにして評価しますか?
現金や普通預金は、被相続人がお亡くなりになられた日の残高がそのまま相続税評価額になります。
被相続人がお亡くなりになる直前に引き出して相続人の手元にある現金や、何らかの事情で相続人の口座に預けていた被相続人の金銭も含める必要があります。
定期預金の場合には注意することがあります。
まず定期預金の評価額自体は、被相続人がお亡くなりになられた日の残高がそのまま相続税評価額になります
しかし、定期預金には、既経過利息というものが存在します。
これは、まだ銀行等から支払われていないものの、被相続人死亡日時点までに発生した定期預金の利息のことです。
既経過利息も相続税評価の対象となりますので、銀行等から既経過利息計算書を取得し、既経過利息の金額も明らかにする必要があります。
不動産はどのようにして評価しますか?
相続税の計算において、不動産の評価はもっとも難しいといっても過言ではありません。
まず、建物については、基本的には被相続人死亡日が属する年度の固定資産評価額が評価額となります。
貸し付けている建物の場合には、固定資産評価額から借家権割合(30%)を控除した金額が相続税評価額となります。
土地の評価方法は、大別して路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、国税庁が公開している路線価に基づいて評価をする方法です。
路線価(1㎡あたりの評価額)に対し、土地の面積を掛け合わせた金額を基準とし、土地の形状や面積、接道条件などの要素を加味して評価額を算定します。
倍率方式は、国税庁が公開している倍率表を用い、評価対象の土地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算するという方式です。
いずれの方式の場合でも、土地を貸し付けている場合には、評価額から借家権割合を控除することができます。
参考リンク:国税庁・路線価図・評価倍率表
相続税の申告と納税はどのようにすればいいのですか? どんなものが相続税の課税の対象となりますか?