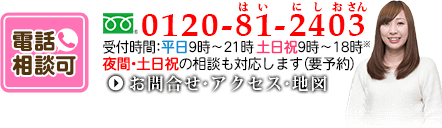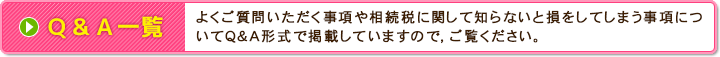お役立ち情報
相続税を減らすために利用できる特例や控除について
1 小規模宅地等の特例
⑴ 小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた宅地を相続した場合で、一定の要件を充たせば、限度面積部分の評価を8割減額できるという制度です。
小規模宅地等の特例を適用できる限度面積は、以下のとおりです。
①特定事業用宅地等の場合 400㎡
②特定居住用宅地等の場合 330㎡
③貸付事業用宅地等の場合 220㎡
①特定事業用宅地等とは、被相続人等が事業のために使っていた宅地等のことをいい、条件を充たしている場合は、限度面積部分の評価を8割減額できます。
②特定居住用宅地等とは、被相続人等が居住のために使っていた宅地等のことをいい、一定の条件を充たしている場合には、限度面積部分の評価を8割減額できます。
③貸付事業用宅地等とは、被相続人等が貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などに限る)のために使っていた宅地等のことをいい、条件を充たしている場合は、限度面積部分の評価を5割減額できます。
⑵ 特例の適用を受けるには申告が必要
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内に相続税の申告をすることが必要となります。
特例を適用することによって相続税の納付がゼロになる場合であっても、申告が必要となる点には注意が必要です。
このように、小規模宅地等の特例を適用するためには、条件や要件が複雑であるため、適用の可否に迷ったら、税理士に相談することをおすすめします。
2 基礎控除
相続税の計算において、全ての相続人が特別な条件なく控除できるものが、基礎控除です。
基礎控除の額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
たとえば相続人が、亡くなった方の配偶者とその子2人の合計3人である場合、基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円となり、この金額までの相続財産には課税されません。
また、このケースにおいて、相続財産の価額が4800万円以下であれば、相続税の申告は不要となります。
3 配偶者控除
相続税額から控除できるものの中に、配偶者に対する相続税額の軽減、いわゆる配偶者控除があります。
配偶者控除とは、配偶者の課税価格が1億6000万円まで、または、課税価格が1億6000万円を超えても法定相続分までであれば、税額控除により、配偶者の納付すべき相続税額がゼロになるという制度です。
配偶者控除を念頭に置いて遺産分割をすることで、納付するべき相続税額が大きく変わることもあります。
特例や控除を念頭に置いた遺産分割が必要な場合には、専門家に相談することをおすすめします。
相続税の課税の対象とならない財産 相続税のみなし相続財産とはどのような財産か